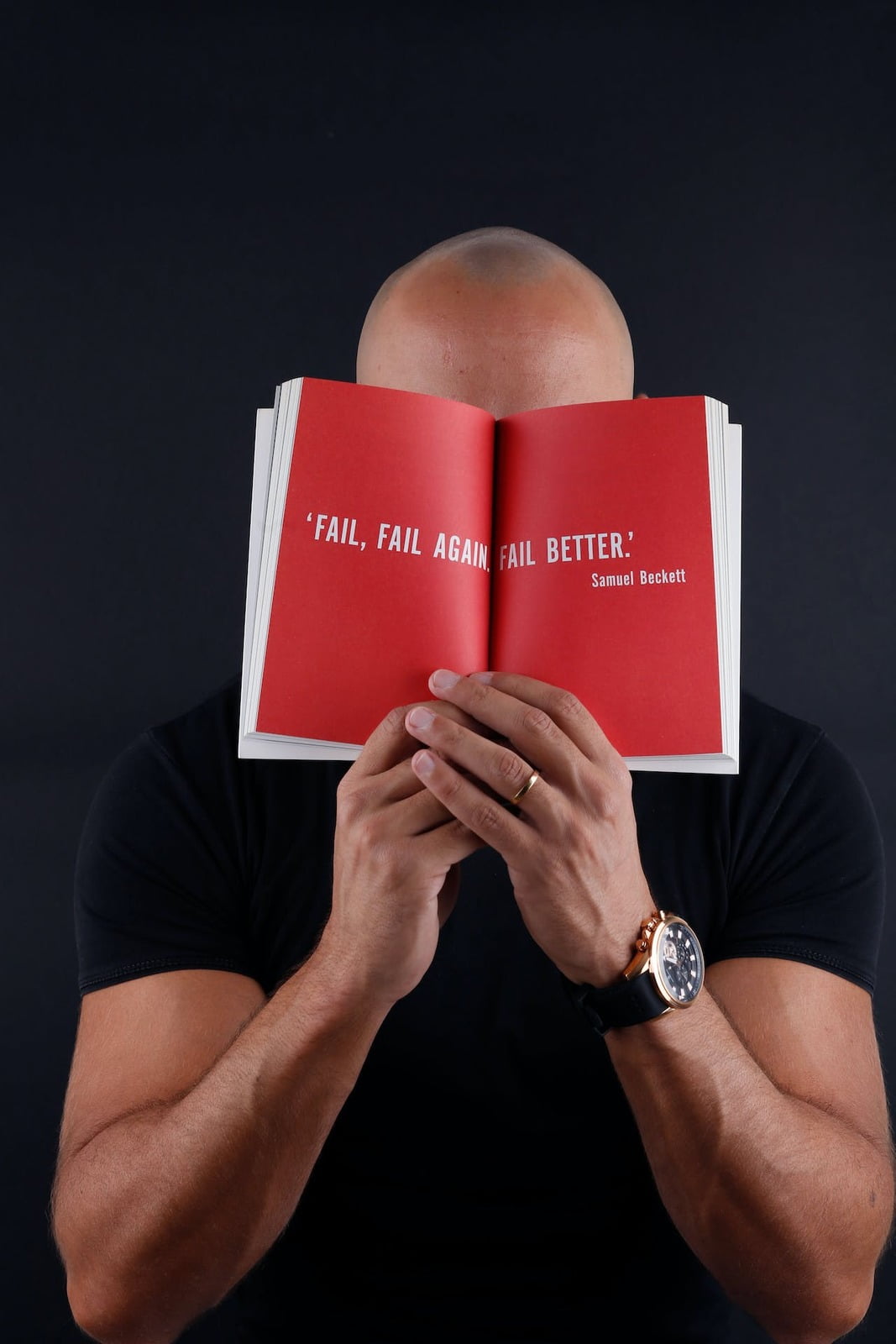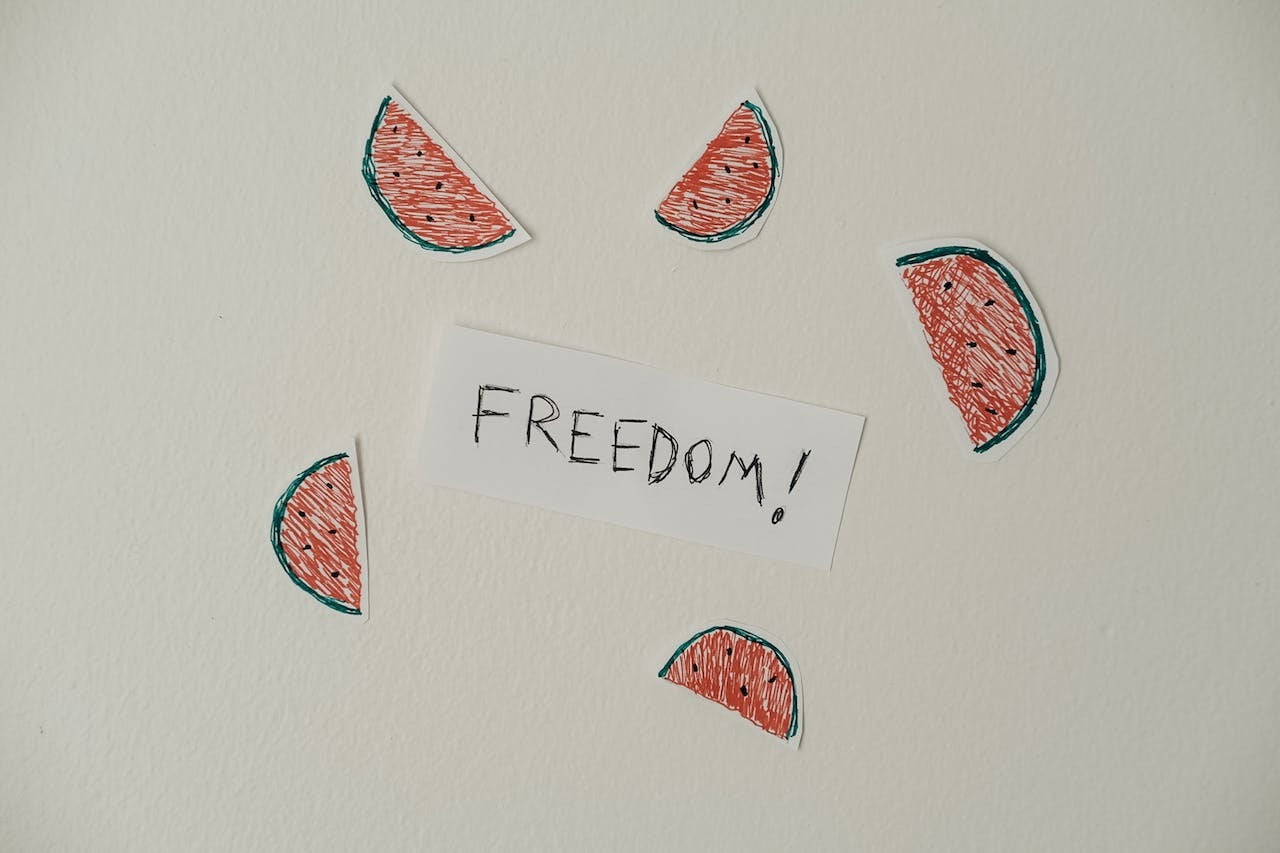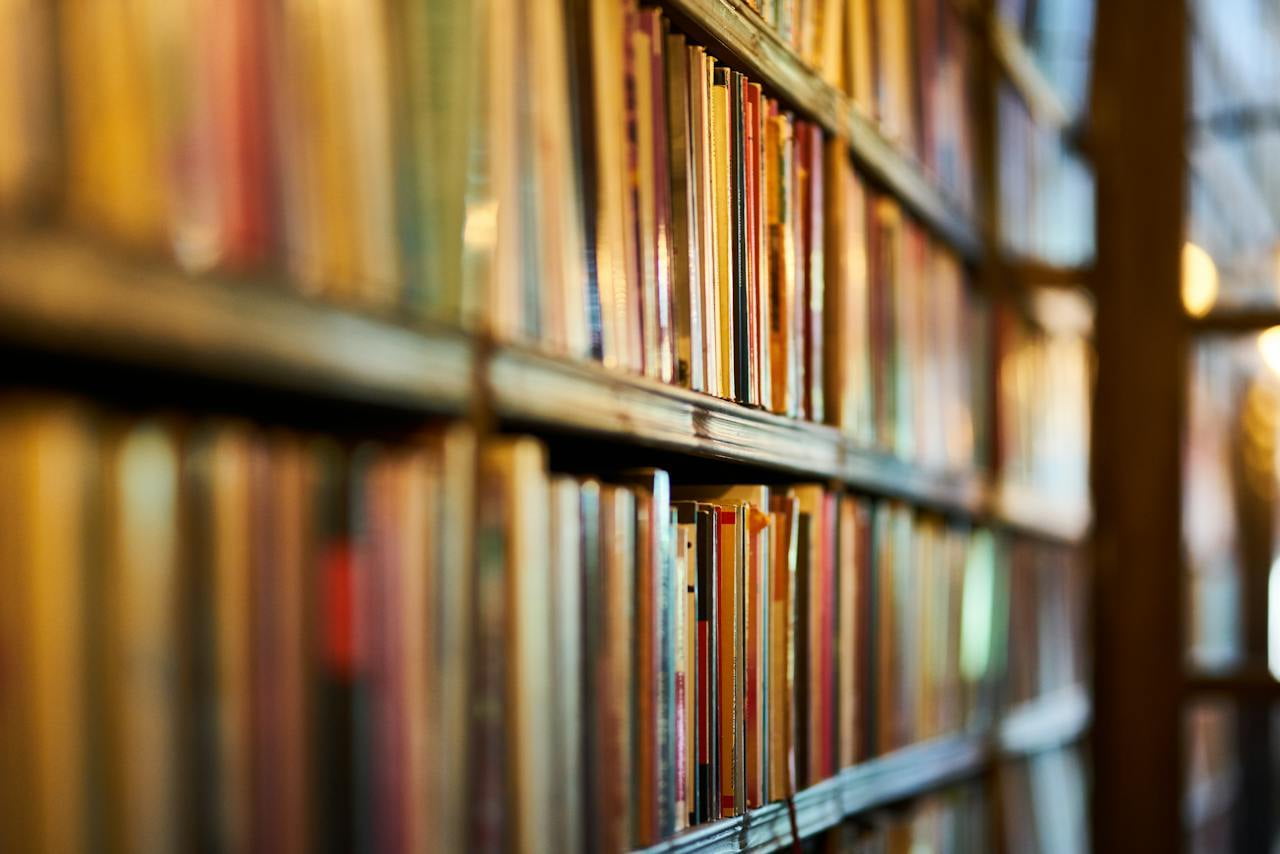ある日、いつものMeditation App(瞑想アプリケーション)のHeadSpace(ヘッドスペース/英語がベースでほかのヨーロピアン言語でも聞けるけど、アジア言語はなし)を聞いていると、アメリカの心理学者のKristin Neff(クリスティン・ネフ)さんのPodcastがあり、心に残りました。
Podcastで、クリスティンさんは、自閉症をもった息子さんがまだ小さい時に、かんしゃくがとまらなくなり、息子本人も苦しいのだろうと思いながらも、自分もつらくて、自分の腕をさすりながら「クリスティン、大変だね、つらいね、がんばってるね」と心の中で言っていると、息子さんにもクリスティンさんの落ち着き...
15.04.24 05:18 PM - Comment(s)